給与計算もご希望の方
福岡で給与計算代行をお探しなら
福岡で給与計算の代行(アウトソーシング)をお探しならば、当事務所にお任せください。
給与計算を間違えてしまったことで、その従業員からの不信感を招き、その後の勤労意欲の低下を引き起こしてしまうことは、会社にとって大きなマイナスです。正確な給与計算を行うことは、会社として「当たり前」の行為であることは言うまでもありません。 ひとり一人の従業員の給与計算、慎重に丁寧に取り組まなければなりません。
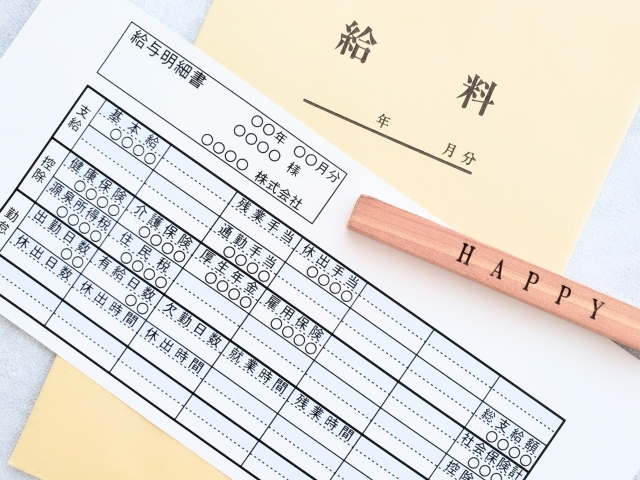
当事務所は税理士事務所兼社労士事務所でもあることから、毎月の給与計算はもとより賞与計算、年末調整まで正確でスムーズな計算を行うことができます。
給与計算代行(アウトソーシング)とは
給与計算代行(アウトソーシング)とは、給与計算業務を代行業者に委託することを指します。
この場合の代行業者とは税理士事務所または社労士事務所を指します。ただし、給与計算においては源泉所得税などの税金を控除する必要がありますので、原則として税理士事務所がその代行業者となるわけですが、社労士事務所において給与計算を代行しているケースも散見されます。これは給与計算において社会保険料や雇用保険料も控除されるわけで、その際には年金事務所またはハローワークへの提出も必要となるからです。それらをリンクさせることで給与計算は正確に算定されます。しかし、給与計算は源泉所得税を控除するため、その算定にあたっては税理士事務所によって行われることが望ましいといえますし、税理士法においても定められています。
現実的には、社労士事務所が給与計算代行を行っているケースが多いようです。ただし、税務署からの指摘を受けて給与計算のやり直しを行わなければならない場合もありますので、税理士事務所にするか社労士事務所にするか慎重に選択する必要があるといえます。信頼できる代行業者にアウトソーシングを行うことで、従業員の方々からの継続的な信頼を手にしていきましょう。
給与計算については代行業者に、社会保険等の手続きは自社でというケースもあります。その場合は綿密な打ち合わせと情報の共有は欠かせません。もちろん、社会保険等の知識を得て慎重な手続きを行っていきましょう。給与計算は代行業者によって受託できる業務範囲が異なりますので、契約前に御社が委託したい内容のサービスが提供されるかを確認する必要があります。
給与計算代行(アウトソーシング)を依頼するメリット・デメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。
当事務所に給与計算代行(アウトソーシング)の依頼するメリット
当事務所に給与計算代行(アウトソーシング)をご依頼いただくメリット3つをご案内してまいります。
①毎月の給与計算・年末調整までスムーズに対応
当事務所は、 税理士事務所兼社労士事務所であるため、毎月の給与計算はもとより賞与計算、年末調整までワンストップで承ります。税務署からのお尋ねや、税務調査となった場合にも対応が可能です。
②税務・労務のプロが徹底サポートで安心
税務・労務の両方の知識が必要となる給与計算を、正確にサポートしますのでご安心してお任せいただけます。
ご希望があれば、給与計算に係る年金事務所やハローワークへの届け出等、労務に係る手続きも承ります。
③給与計算の負担を大幅に軽減
給与計算に係る煩雑な事務作業から解放され、本業に集中することができます。
税理士事務所と社労士事務所を別々にご契約されているならば、当事務所と契約していただくことで税務と労務をワンストップで解決でき、給与計算に係る連絡のお手間とコスト削減も可能です。
実績と実例
当事務所は、従業員20人程度までの会社、会社設立したばかりの会社、個人事業主を応援しております。 下記は給与計算代行を承っている企業様の一例です。
| 会社名(敬称略) | 業種/規模 |
|---|---|
| R株式会社 | 建設業/10人 |
| L株式会社 | 営業/20人 |
| 株式会社T | 物流業/25人 |
当事務所の給与計算代行(アウトソーシング)のサービス内容
当事務所が対応するサービス詳細をお伝えしてまいります。
- 毎月の給与計算-当事務所にお送りいただいた勤怠データを元に、残業代、各種手当、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税などの算出を行います。
- 賞与月の賞与計算-会社ごとに定められた規程を確認したうえで賞与計算を行います。
- 法定調書合計表の作成
- 給与支払報告書作成
給与計算代行業務の流れ
- 勤怠給与計算データの受領(メール・郵送・FAX)
- 当事務所にて給与計算
- 給与計算関係書類一式をお客様へ送付(メール・郵送・FAX)
- 退職者の源泉徴収票作成
年末調整代行サポートの流れ
当事務所の年末調整業務は以下の流れで行います。
- 回収済みの申告書の内容及び添付資料の確認
- 不備・未回収・不足資料のリストアップ及びご共有
- 給与チェック用データをお客様へ送付(メール・郵送・FAX)
- 年末調整控除データの作成
- 年税額の計算及び12月最終給与への過不足税額計算
- 源泉徴収票の発行
給与計算代行(アウトソーシング)のご依頼から給与計算代行の流れ
- ヒアリング
お客様の「お困りのこと、わからないこと」をお聞きしたうえで、給与規程や締め日、支払日などを確認いたします。給与計算業務の範囲などお客様のご希望をお聞かせください。 - 見積書の提出
お客様の現況、ご希望をもとに見積書を提出いたします。 - ご契約
見積書にご納得いただけ、条件が合えばご契約となります。 - 事前打ち合わせ
給与計算に必要なデータおよび受け渡し方法の確認等、給与計算代行を承るうえで必要になることを打合せで確認いたします。 - 給与計算代行の実行
いただいた給与計算データにもとに、給与計算代行を行います。
当事務所と契約するメリットや特徴をお知りになりたい方は、こちらのページをご覧ください。
給与計算を行う前の確認事項
給与計算を行う前に確認しておくべき事項についてお話いたします。
給与規程の確認
給与規程から賃金体系を確認していきます。
- 基本給-決定要素の大枠を明記します。
- 役職手当-各職位に基づき金額を明記します。
- 通勤手当-公共交通機関の場合は定期代1か月分などを、マイカー利用の場合は通勤距離により所得税非課税限度額が決められているのでその範囲内と明記します。
- 割増賃金-1か月平均所定労働時間数を給与規程に明記することが望ましいです。
住宅手当を割増賃金の基礎から除外できるようにするためには、賃貸住宅居住者の場合には家賃の○%というように明記しておくことが求められます。 - 欠勤控除-年平均月所定労働日数を給与規程に明記することが望ましいです。
(基本給+役職手当)÷1か月の平均所定労働日数×欠勤日数 - 賞与計算-各人ごとに賞与金額が決定され、支給の有無については支給時期を延期し、または支給しないことがあると明記することが望ましいです。
控除項目の確認
給与金額から下記のものが控除されます。
- 源泉所得税-その年分の扶養控除等申告書と源泉徴収税額表が必要です。
- 住民税-5月下旬に市町村から送られてくる特別徴収税額の決定通知書が必要です。切替届の提出も必要となります。
- 雇用保険料-給与総額に1,000分の3(令和5年10月から1,000分の5)乗じた額となります。
- 健康保険料及び厚生年金保険料-標準報酬月額に都道府県別に定められた保険料率を乗じた額の半分です。
- 他には労使協定により賃金からの控除が定められたものです。
支払方法の確認
給与規程には、月次給与及び賞与について、計算期間と支払日を明記する必要があります。
月次給与について
月次給与の場合、賃金の締切日と支払日を確認します。割増賃金や欠勤控除の計算にはある程度の期間が必要ですので、賃金締切日を当月20日とし支払日を当月末日などとすることが賢明です。
賃金締切日を当月末日とし支払日を翌月10日とすることも可能です。その場合においては社会保険の月額変更届で注意する点が出てきます。
賞与について
賞与については、在籍要件と支給日要件を確認します。
例えば、支給対象期間である1月1日~6月30日の期間まで在籍していた場合には、「賞与の支払日である7月10日に在籍していなくても支給するものとする。」あるいは、「賞与の支払日である7月10日に在籍しているときに支給するものとする。」となどいう要件を設けることになります。
税務上で疑義が生じやすいのは支給日要件です。前者の「賞与の支払日である7月10日に在籍していなくても支給するものとする。」を適用したほうが望ましいと言えます。
毎月の給与計算の流れ
1.勤怠項目の計上
賃金台帳に記入が必要な出勤日数、総労働時間、時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間についてタイムカードから把握します。これは割増賃金を計算するためです。
次に、欠勤日数、遅刻時間、早退時間などもタイムカードから把握します。これは、日給月給制における勤怠控除計算のために必要です。
2.支給項目の計上
下記の金額の集計を行います。
- 固定給(基本給、役職手当、通勤手当など)
- 変動給(時間外手当、皆勤手当、休日手当、深夜手当、欠勤控除など)
3.控除項目の計上
社会保険料
- 健康保険料(標準報酬月額に都道府県単位で設定された保険料率を乗じた金額の半分)
- 介護保険料(40歳以上65歳未満の人が対象)
- 厚生年金保険料(標準報酬月額に保険料率を乗じた金額の半分)
月の末日に被保険者である人は、その月の保険料が発生し、翌月の月次給与分から上記の金額を徴収することになります。例えば10月の末日までに被保険者になった人は、10月が資格取得月となり「社会保険被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出する必要があります。この場合、11月の月次給与分から10月分の社会保険料を徴収することになります。
逆に、別の人が11月末日に退職した場合には、翌月の12月が資格喪失月となり「社会保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。この場合、11月の月次給与分から10月分及び11月分の社会保険料を徴収することになります。
雇用保険料
総支給額に被保険者負担の保険料率を乗じた金額を徴収することになります。
令和5年10月から被保険者負担の保険料率は1,000分の5に改定されます。
徴収時期については、3月の月次給与が月末締めで翌月4月10日支給であれば、4月10日支給時に3月分の雇用保険料を徴収します。「労働保険年度更新申告」において、給与総支給額の集計期間が4月発生分から翌年3月発生分となっている点と符合します。「雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届」「離職票の申請」なども雇用保険の対象者についても適宜の届け出が必要となります。
源泉所得税
前提として、その年分の扶養控除等申告書と源泉徴収税額表が必要となります。
まず、給与の総支給額から非課税の給与収入である通勤手当を差し引いて給与収入額を求めます。さらに給与収入金額から社会保険料・雇用保険料を差し引いて「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算する必要があります。
次に、源泉徴収税額表の左の列の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の金額の範囲内を選択し、扶養親族等の数に記載された金額がその月の源泉所得税額となります。
住民税
前提として、毎年5月下旬に市町村から会社に送られてくる特別徴収税額の決定通知書が必要となります。
そこには各人別の月ごとに徴収する住民税額が表記されています。新しく入社した人が給与からの天引きを希望した場合には「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を市町村に提出します。
その他
上記に示した控除項目以外の金額を給与金額から控除する場合には、労使協定が必要です。旅行積立金、財産形成貯蓄金、会社立替金などがこれにあたります。
社労士事務所では税務調査に対応できません
ご覧いただきましたように、給与計算は大変煩雑な業務です。税務だけでなく労務の知識も必要なことがお分かりでしょう。
年金事務所やハローワークへの届け出と給与計算はセットで進めていく必要があります。労務に係る手続きも必要なことから、税理士事務所単独での給与計算は困難といえます。
だからといって、社労士事務所に給与計算を依頼したとしましょう。一部の社労士事務所ではこの年末調整業務も行っているようです。ところが、給与計算の終結業務である年末調整を社労士事務所が行うことは税理士法違反となります。税務署からのお尋ねや、いざ税務調査となったときに社労士は何ら対応できません。高い報酬を払ったのに責任を取ることができないのであれば、社労士事務所に依頼することは大変な無駄であり、多大なリスクを伴うことなのです。
当事務所だからできる給与計算と年末調整
税務と労務の「分からない、困った」を一元的に解決できるワンストップ事務所の当事務所なら、給与計算及び年末調整をスムーズかつ正確にお任せいただけます。頼れる参謀役としてより一層ご活用いただけると考えます。
是非、他のページ「税理士をお探しの方」「社労士もご希望の方」もご覧ください。
料金表(金額はすべて税別表示です)
給与計算・年末調整を行う場合の料金
| プラン | 報酬料金 |
|---|---|
| 毎月の給与計算 | 5,000円+1,000円×人数 |
| 賞与月賞与計算 | 1,000円×人数 |
| 法定調書合計表 | 10,000円 |
| 給与支払報告書 | 3,000円×人数 |
| 報酬等支払調書 | 2,000円×人数 |